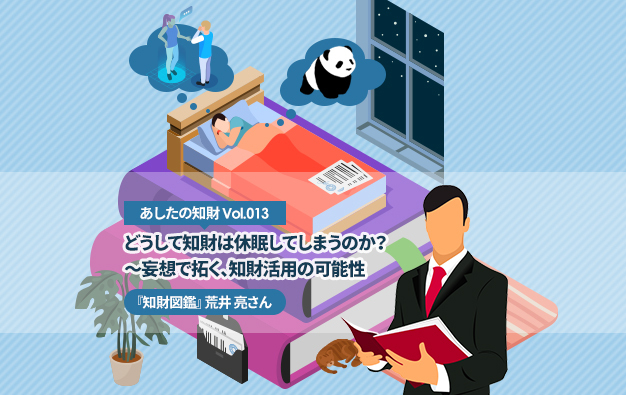「知財をどうやって、一般の方にわかりやすく理解してもらうか?」
これはあらゆる知財関係者に共通する課題でしょう。
企業知財部なら、発明者や事業部のメンバーに。
特許事務所なら、クライアントに。
大学など教育機関なら、学生に。
特許庁なら、ユーザーに。
さまざまな「知財業界外」の人々に、知財の価値を知ってもらいたい場面があります。
もちろん、「企業知財部と特許事務所との専門的なやり取り」で完結する知財の仕事もたくさんあるでしょう。
ただ知財の中身は、人間の「知的創作物」。研究者・エンジニア・クリエイター・知的創作物のほとんどは知財業界外の人の手により創造されています。
つまり知財は必然的に「業界の外で生み出され、業界の外で活用される」もの。知財業界だけで完結しようがなく、外との関係性ではじめて価値が生まれます。
しかし、知財業界の外とのコミュニケーションはなかなか難しい。我々 Toreru Media も「知財を身近にする」をテーマに活動していますが、知財という専門分野をわかりやすく伝え、社会で活用してもらうためにはどうしたら良いか?答えを模索する毎日です。
また、人類の英知としての「知財」と、法律で保護される「知的財産権」とは同じようで異なるもの。知的財産権ばかり見ていると、見落としてしまう「知財」もありそうです。
そこで今回は、「知財と事業をマッチングさせるクリエイティブ・メディア」であり、専門家でなくても活用できるオープンな「知財データベース」を構築されている『知財図鑑』の荒井 亮編集長にお話を伺いました。
<荒井 亮氏プロフィール>
クリエイティブ会社にてライブ配信事業のプロデューサーとして番組の企画制作、各種アライアンスやチームビルディングを担当。その後、Konelにジョインし「日本橋地下実験場」を中心としたプロジェクトに参画。2020年1月より株式会社知財図鑑共同代表、『知財図鑑』編集長。
☆『知財図鑑』公式サイト:https://chizaizukan.com/
『知財図鑑』がなぜできたかや、『知財図鑑』が考える知財の枠組み、また知財を社会に実装するキーとなる「妄想力」など、知財の未来につながる話が満載です!
1、『知財図鑑』はなぜできた?
―本日は『知財図鑑』の編集部がある、東日本橋のオフィスにお邪魔しています。編集部は(株)コネルのオフィスと共通なのですね。まずは『知財図鑑』と(株)コネルの関係について教えてください。
荒井さん:『知財図鑑』は法人化もしているのですが、もとは(株)コネルを母体とした会社です。コネルは「未来を実装する、越境クリエイター集団」と自己定義していますが、より分かりやすく言えば、技術×アートの掛け算に強いクリエイティブ会社です。
クライアント企業から技術や課題といったお題をいただき、「クリエイティブ」を掛け算して世の中にアウトプットする。例えば、私の後ろに展示されている『サイバー和菓子』。
―これ、ネットで見たことがあります。風速、気圧、温度といった気象データをもとに異なる形状の和菓子を出力してくれるんですよね。
荒井さん:和菓子は日本の暦に合わせて作られ、季節の訪れを味わうところがありますよね。ただ、最近は温暖化もあって実際の気候と暦が合わなくなってきている実感があります。
そこで、「気象データをベースに和菓子を3Dプリント」して、現実の気候と連動する和菓子を作り出すというものです。過去の「あの日」を再現することもできるし、和菓子という伝統文化をテクノロジーで拡張することにもなります。合わせて社会課題である「気候変動」を可視化することもテーマにしています。
―3Dプリンターと気象データがあっても、それを和菓子にするというのはなかなか考えつかないですよね。しかもアイデアだけじゃなくて、実際に和菓子を作ってしまうとは。
荒井さん:気象データもそのまま和菓子にできる訳ではないので、風速・気圧・気温といったデータを、人の手では作れないような形の和菓子に出力する独自アルゴリズムも開発しました。コネルはアイデアや妄想を具現化するところが得意な会社です。
―エキサイティングですね!そんなコネルから『知財図鑑』が生まれたきっかけは?
荒井さん:クライアントから色々なご相談をいただく中で最近多いのが「この技術、当社で開発した自信作だけどなかなか良い使い道が見つかってない。一緒に考えてもらえませんか?」という相談です。
例えば、パナソニックさんからは「4名同時に接触認識できる、マルチタッチモニター」という技術をお題として頂きました。ディスプレイをタッチしている人が4人のうち誰かまで識別できる優れた技術だったのですが、相談いただいた時点の試作品では「モグラたたきゲーム」がインストールされていました。
―誰が叩いたかわかるモグラたたきゲーム。確かに便利ではありますが、うーん、何回も遊ばないかな。
荒井さん:技術検証用途としては有用ですが、社会でのユースケースとしては正直弱いよね・・と。何年も研究者の方が心血を注いで開発し、技術的にはいいものができているのに、これでお蔵入りはもったいない。
そこで違うものを作ろうと、できたのがこちらの『Transparent TABLE』です。
―「手ぶらで話そう。」というコピーがありますが、どういうテーブルなんでしょうか?
荒井さん:会議のシーンを思い浮かべてほしいのですが、通常はパソコンを持ち寄って、プロジェクターをセットしてホワイトボードに手書きして、議事録を共有するなど付随する作業が多いじゃないですか。日程調整もひと手間ありますよね。
このテーブルは、パナソニックの4人接触認識のマルチタッチモニターに、会話を画像でリアルタイムに表示できるAPIを組み合わせています。
そのため、テーブルを囲んでしゃべっているとキーワードを自動で拾ってくれ、対応する画像がどんどん出てくる。アイデアが促進できるし、その画像から気になるものを参加者がタッチするとピン止めすることもでき、そのタッチ履歴が自動的に保存されるという仕組みです。
―タッチした画像が、参加者の議事メモになるのですね。
荒井さん:これが「パナソニック創業100周年イベント NEXT100 」で「手ぶらで打ち合わせができる未来の会議テーブル」として展示されました。「このテーブルが例えば小学校にあったら、国会にあったら、どう使われるのだろうか?」という問いかけもして、来場者に自由にコメントしてもらいました。
とても面白いプロジェクトだったのですが、このような「技術の使い道相談」が増えてくると、コネルで受けられるキャパも限りがありますし、プロトタイピングがいくら早いといっても、使い道のアイデアを整理し、試作するのには数か月は必要です。
―そうなると面白い技術があっても検討の「順番待ち」になるし、手が回らずそのまま死蔵されてしまう技術もありますね。もったいない。
荒井さん:技術の使い道について、コネルだけでなくもっとオープンに議論ができ、かつスピーディーに社会に問いかけられる仕組みがあるといいなと。
そのためには、いろんな技術が集まったデータベースがあり、そこから自由に発想を広げられる仕組みがあるといいよねという話になり、『知財図鑑』のアイデアが生まれたのです。
ー技術のデータベースとしての構想がまずあったと。ただ、J-PlatPat のような公的な特許データベースもすでにあるじゃないですか。それでは上手くいかない?
荒井さん:単純に、自分たちが既存のデータベースを使おうと思えなかったんです。コネルはエンジニア・クリエイターなど特許を専門としないメンバーがほとんどですが、自分たちが技術を調べたいときに J-PlatPat で調べようとしても、ほとんど分からない。
例えば、「視線検出」というキーワードで技術を探そうとしても、タグという形で整理されているわけではないので、検索でヒットしたドキュメントで「どこに視線検出がある?」と探さなければならないですし、文章も読みにくく、必死に読み解いても「あれ、これ関係ない技術だな」とか・・。
ー確かに既存の特許データベースは、クリエイティブの参考のために文献を探し、そこから活用法を考えていく用途には向いていないですね。
荒井さん:そうですね。掲載されている特許明細書も、専門外の人間には理解困難です。また、『知財図鑑』でいう「知財」とはべつに特許だけに限っていません。人間の知的創作物を「知財」ととらえるなら、未出願の技術・ノウハウでも十分活用の可能性はある。
そこで、自分たちが知財を分かりやすく探せるデータベースが欲しいなと。
そのデータベースでは、ワード検索だけでなく「タグ」で知財が分類されているといいなと。例えば「新素材」「ソフトウェア」「環境」など、特定のテーマのタグを見ることで、関連知財を一気見できます。
ー現在の『知財図鑑』で実装されている機能ですね。タグをクリックして登録されている知財をざっと眺めているだけでも、アイデアが湧いてきそうです。
荒井さん:図鑑って眺めているだけでも発見があるし、楽しいですよね。また、ウェブデータベースだからどんどん情報を足していける。『知財図鑑』は成長する図鑑です。
ー『知財図鑑』がサービスとして実際に立ち上がったのはいつからなんですか?
荒井さん:最初は、2019年12月に秋葉原UDXで開催された「Yahoo! HACKDAY 2019」にプロトタイプを出しました。そこで好評をいただいたので、実際にサービスとして立ち上げようかと。
12月のプロトタイプがβ版で、2020年1月には『知財図鑑』を法人化。掲載知財が100を超えた2020年5月には、本格ローンチとしてリリースを出しています。
ーフットワークが軽い!荒井さんが編集長になったのは?
荒井さん:コネルはクリエイティブ会社なので常にみんな何かしら忙しくて、その時に動けるのが僕しかいなかったんですね(笑)
ただ、自分としても「クリエイターが再解釈することで、みんなが気軽に活用できる知財データベース」はニーズがあると感じていましたし、面白い知財がそのまま「死蔵」されていくのは違う、多くの人が知って活用されると良いと感じていましたので、やるならしっかりコミットしたいなと。
立ち上げ期から法人化しているのも、「事業」として本気で取り組もうとコネル代表で知財図鑑共同代表の出村と話をした結果ですね。
2、知財ハンターが集める「すごい知財」たち
―このインタビューは2022年6月に収録していますが、β版の立ち上げから約2年半経過して、『知財図鑑』はどれぐらいのサイトに成長したのでしょうか。
荒井さん:平均して月間約30万PVほどです。データベースとしての「掲載知財数」も伸びていて、現在では約700件の知財を掲載しています。
―凄く順調に伸びていますね。このグラフを見ていると2021年に15万PVから30万PVぐらいまで倍増していますが、何か理由があるのでしょうか。
荒井さん:「掲載知財数」を伸ばすことには当初から取り組んでいますが、それとは別に2021年から「ニュース記事」にも力を入れだしたんですよね。今は営業日には何かしら新しいニュースを紹介できるようにしています。
また、新たに掲載した知財やニュース、イベントを紹介するメルマガも毎週1〜2回発行していて、毎回約4000通配信しています。そこから「この記事、読んでみようかな」と訪問してくれるユーザーも多いですね。
あとは Smart News や Gunosy といったニュース配信サービスにも記事を配信できるようになり、知財業界外の人が手軽にスマホでアクセスし、興味を持って見に来てくれる導線も確立しました。
―知財業界外の人のアクセスが増えているのは熱いですね。
荒井さん:『知財図鑑』には、「新規事業にチャレンジする人々が、すでに存在する知財の存在を知らずにアイデアの実現をあきらめてしまったり、『車輪の再発明』のように無駄な労力を費やしたりする機会損失をなくす」というミッションがあるので、知財の専門家以外の人に見てもらうことはとても重要です。
―この図の上がビジネスの事業者、下が知財保有者ってことですね。確かに、1つの会社でも事業部門と知財部門が切り離されてしまっていることは多いですし、社会全体で考えると、「断絶」は深刻・・。
荒井さん:立ち上げ時の『知財図鑑』のターゲットはあくまで「非研究者のクリエイターやビジネスパーソン」だったのですが、今はさらに一般の方々、それこそ高校生や主婦の方にも見てもらいたいなと。
暇つぶしで Smart News を開いたときに、『知財図鑑』の記事を見かけてみんなが自然とアクセスする・・そういう段階まで持っていければ、知財と社会の断絶は少なくなるのかなと感じています。
―ニュースにも興味深いものが多いですが、『知財図鑑』の最大の魅力はやはりメインコンテンツである「知財データベース」の読みやすさだと思います。データベース作りの工夫について教えてください。
荒井さん:まずは掲載情報のフォーマット化ですね。掲載されている知財にはNo.500のような通し番号が付くほか、「概要」「なぜできるのか?」「相性の良い分野」「この知財の情報・出典」という統一フォーマットで情報を載せています。
また、一部の知財には「妄想プロジェクト」という項目もあり、これはその知財にどういう活用法があるのかを『知財図鑑』側で自由に考え、イラスト化して掲載しています。
掲載知財の項目を統一したことで、ライターにも執筆を依頼しやすく、たくさんの知財を掲載することが可能になりました。またユーザーが閲覧する際にも「この知財の特徴は何か、どの分野で活用しやすいのか」と理解しやすくなったと思います。
また、先ほどの「タグ」や「産業分野」で絞り込みすることで、関連知財をまとめて閲覧できます。
―『知財図鑑』のデータベースには、依頼を受けて載せるのでしょうか?
荒井さん:2つのパターンがあって、1つはスポンサー記事という形で、知財の所有者や企業から依頼を受けて掲載する場合。図鑑の右上に「Sponsored」という表記がついています。
もう1つは「知財ハンター」が独自に集めてきた情報から、『知財図鑑』の編集部がピックアップして掲載する場合です。
―その「知財ハンター」とは、『知財図鑑』の社員なんでしょうか?
荒井さん:もちろんコネルや『知財図鑑』のメンバーが中心ですが、外部の方の参加も歓迎しています。「知財ハンター」の役割は、世の中から「すごい知財」を発見し、世の中に新たな活用方法を提案すること。
ここでいう「すごい知財」とは、「応用可能性が高く、現実に利用可能な先人の知恵」と広く定義しており、特許に限定せず、あらゆる技術・アイデア・プロダクト・デザインが対象となります。
現在、約50名の方に知財ハンターとしてご参加いただいています。
―世の中から「すごい知財」を探してくるのが、まずは「知財ハンター」の役割なのですね。その発掘してきた知財を、どうやって『知財図鑑』で記事化しているのでしょうか?
荒井さん:コネルのSlackに「知財ハンター」のチャンネルがありまして、そこに面白そうな知財を見つけたら、知財ハンターの方に自由に投稿いただいています。
投稿のときに、@ip_loggerというタグを付けてもらっているのですが、このタグをシステムが自動で拾い、Google スプレッドシートに自動でリスト化されます。
そのスプレッドシートの内容を定期的に編集部で確認して、面白い知財があれば「これ掲載しよう」とか、「どういう妄想プロジェクトがあり得るんだろう」と討議して、『知財図鑑』に載せるコンテンツを決めるのが、一般的な流れです。
幅広い「知財ハンター」の方々が未知の知財を発掘していくことで、『知財図鑑』の多様性は成り立っています。これからも色々な分野のハンターを増やしていきたいので、関心がある方のご応募をお待ちしております!
参考:知財ハンターとは?
3、“妄想”と“プロトタイピング”が知財の可能性を拓く
―「知財ハンター」のほか、さきほど「妄想プロジェクト」というキーワードが出ましたが、これも『知財図鑑』の大きな特色だと思います。もう少し詳しく教えてもらえますか。
荒井さん:「妄想プロジェクト」とは、実在する知財をベースに、知財ハンターや編集部が社会での新しい活用法を“妄想”し、ビジュアル化する取り組みです。ビジュアルはイラストレーター(妄想画家)に依頼し、新規で絵を描き起こしてもらっています。
掲載している知財全てに「妄想プロジェクト」のビジュアルを付けられれば良いのですが、マンパワーの限界もあり、全件には実現できていません。ただ、現在でもすでに96件の「妄想プロジェクト」を公開しています。
ーぱっと見ただけでも、面白い妄想プロジェクトがたくさんありますね!荒井さん的にお気に入りの妄想プロジェクトはあるでしょうか?
荒井さん:1つは『さわれる動物園』ですね。図鑑No.280「感性素材「α GEL」を用いた感触の見本帖」から生まれた妄想プロジェクトなのですが、ちょうど「α GEL」のサンプルがオフィスにあるので、触ってみてください。
ーあっ、12個のサンプル全て、硬さや触感が全然違いますね!ヘビ皮っぽい触感もあれば、人肌?っぽい生々しい手触りもあり。
荒井さん:これは(株)タイカさんからのご相談案件だったのですが、12個のサンプルそれぞれに「焼く前のお餅」や、「ずっしり濃厚練羊羹」などなど、イメージしている違う触感がありました。
この見本帖をベースに新しい活用法がないか “妄想” を広げたところ、「さわれる動物園」というアイデアが生まれました。
私も4歳の娘がいて、動物が好きなのですがコロナ禍で上野動物園もしばらく閉園しており、再開しても入場制限がかかっていて昔ほどは気軽に入れなくなりました。
また、動物園に入っても実際にパンダやワニを触ることはできないですから、この「さわれる動物園」があれば、子供たちも見るだけでない新しい感覚の切り口が増えて、それこそ「触育」みたいな新しい概念も生まれたら面白いなと。
実際に動物園をクライアント先に持つ代理店の方から連絡もいただき、打合せ資料にこの「妄想プロジェクト」のイラストがそのまま採用されていて、「こういう使い方をしてほしかった」と思って嬉しかったですね。
ー知財を社会に実装するための「自由な提案」が妄想なら、それを見た人からさらに話が広がっていくのはまさに理想的ですね。実際に妄想プロジェクトが現実化した例はあるのでしょうか?
荒井さん:『SHUTTER Glass』は妄想がカタチになった好例ですね。
元になった知財は、図鑑No.213「高速カメラ物体認識技術」で、高速移動する被写体を、動きを止めることなくリアルタイムで認識・撮影するNECさんの技術です。
この技術には、工場ラインで自動的に不良品を識別したり、流れてくる金属の中からレアメタルを発見するなどの用途がすでにありましたが、さらなる用途を考えてほしいという依頼がありました。そこで知財ハンターと研究者の方々とで一緒にワークショップを実施し、「日常の美しさを自動的に切り取ってくれるメガネ」という妄想が生まれました。
ーメガネ型のウェアラブル端末、いわゆるスマートグラスですね。どのように機能するのでしょうか?
荒井さん:「日々せわしなく生活している中で、視界には入っているけれど見逃している美しいものはたくさんあるんじゃないか?」というのが妄想の出発点で、例えばきれいな花や景色があっても、考え事をしていたりスマホを見ていたりすると意識には入ってこない。
そこで、スマートグラスのカメラに飛び込んできた映像をリアルタイムで画像認識し続け、その人が「美しい」と感じるだろう画像を位置情報とともに保存する。
1日終わって家に帰ってログを見ると、自動保存していた画像を「ここにはこんな花が咲いていました」みたいな形でスライドショーで見せてくれるプロダクトアイデアです。
ー単なる1日のログだけでなくて、「美しさ」のようなテーマがある点がエモいです。「その画像が美しいと感じるかどうか」の識別はどう行うのでしょうか?
荒井さん:人それぞれの感性イメージを「心的テンプレート」として、画像化・数値化する技術を大阪大学が別に開発されており、その技術を応用することになりました。
『SHUTTER Glass』の試作品では、メガネを通してユーザーが見る絵画の好みから、そのユーザーの「心的テンプレート」を生成し、その人が美しいと感じるだろう花を提示するデモを実装しています。
ーすでにプロトタイプがあるとは、一気に実用化できそうな感じが出てきました。
荒井さん:これはコネルの強みなのですが、オフィスの地下に“日本橋地下実験場”というファブリケーション(ものづくり)スペースがありまして、「爆速プロトタイピング」を実現しています。せっかくなので、ラボにも行ってみましょうか。
ーまさに秘密基地って感じですね!ここで様々なプロトタイプが作られた?
荒井さん:このラボだけで完結する場合もあれば、外部のクリエイター・企業とも連携してプロトタイプを作るケースもあります。外部パートナーとの連携もコネルや『知財図鑑』の強みですね。
完成した『SHUTTER Glass』のプロトタイプはNECさんの共創拠点 NEC Future Creation Hub KANSAIで展示されているほか、商品化に向けてさらに検討が進んでいます。
ー単なる妄想に終わらず、実用化に向けてカタチにする作業も進んでいるのは素晴らしいですね。
4、勝手に「妄想」したら起こったコト
―しかし、ユニークな「妄想プロジェクト」をたくさん考えだすのは大変ですよね。アイデア出しに上手いやり方があるのでしょうか。
荒井さん:『知財図鑑』では、毎週金曜日に「妄想大喜利会」というのをオンラインで開催しています。朝15分ぐらいの短い時間なのですが、参加メンバーに「お題となる知財」を共有して、自由にネタを考えてもらうというものです。
―どういうメンバーが参加しているんですか?15分だと結構短いですよね。
荒井さん:『知財図鑑』の編集チームやコネルの関係者、外部のクリエイターや知財ハンターにも飛び入りで参加してもらうこともあって、大体10名前後です。
時間は皆さん自分の仕事もあるのと、毎週の活動なので「時間をかけすぎない」ということも意識しています。
―「妄想大喜利会」はどのように進行されているんでしょうか。
荒井さん:まずお題となる「知財」を1つ決めまして、事前に参加メンバーにSlackで共有します。例えば「人物を再現できるAI技術」などに対してなんとなくネタを考えておいてもらう。
そして、「妄想大喜利会」の冒頭で、軽くどういう技術かの説明をして、オンラインの共有ドキュメントに「その技術を使った大喜利ネタ」を参加者が自由に書いていきます。書くのは5分ぐらいですかね。
―NHKの紅白で「AI美空ひばり」とかありましたよね。大喜利シートをみると・・「歴史上の偉人を赤ちゃんから育てるシミュレーションゲーム」とか、「ひろゆきVSひろゆきの論破対決」とか、確かに自由だ。ちょっとその対決は見てみたいです。
荒井さん:本当に思いついたアイデアをガーっと書いてもらうのがポイントで、適当でいいんですよ。このシートを見つつ、参加者でさらにネタだしをします。
「歴史上の偉人なら、バーチャル空間で戦わせる天下一武闘会が見たい」とか、膨らませていって15分ぐらい経ったら終わり。話が盛り上がったものは、『妄想プロジェクト』としてイラスト化もしています。
―「妄想大喜利」が『知財図鑑』のコンテンツにもフィードバックされているんですね。
荒井さん:「大喜利」は瞬発力で、時間が限られているからこそ、飛躍したアイデアが出やすい効果があります。また、「妄想」という言葉を使うことで、参加者のアイデア出しに対する心理的なハードルを下げるよう工夫しています。どんなにくだらないと思うネタでも言って良いんだよと。
―確かに、「妄想」って掲げてあるから自由に言えるって雰囲気は感じます。想像でも、空想でもなく、「妄想」じゃないと出ない自由さ。
荒井さん:妄想って言葉は、「あり得ないことをあり得ると信じる」とか、「根拠がないことをとりとめもなく想像する」とか、マイナスな意味がありますが、逆に「あり得なくても良い」、「実現可能性が薄くも良い」って背中を押す力もあるなと。
―普通に「想像」できるものが現実化しても驚きは少ないけど、「妄想」が現実化したほうが感動するじゃないですか。「えっ、そんなことできちゃうの!?」って。
荒井さん:実は、『知財図鑑』の「妄想」は、既存の「知財」を出発点にしているので、根拠がまったくなかったり、あり得ない話ではないんです。ただ、普通に考える「想像」の枠からははみ出して、世の中にインパクトがある知財活用を提案していきたい。
大企業の方とプロジェクトを進める際に、「うちの会社の看板で『妄想』なんてリリースを出すと、社内外から「不真面目な!」と怒られてしまうけど、『知財図鑑』との共同プロジェクトという形なら『妄想』という言葉も受け入れられる」なんて話も聞きますから、「妄想」を看板に掲げるのは『知財図鑑』の1つの役割として大事だと感じています。
―あと『知財図鑑』ですごいなと思うのは、依頼を受けた仕事としてじゃなく、「勝手に妄想」しているパターンも結構あるじゃないですか。そういうのは、妄想元から怒られることはないんでしょうか?
荒井さん:今のところ怒られたことはないですね(笑)。公開情報をもとに独自に「活用方法」を考え、イラストも描きおろしやGettyimagesの有料画像などを使用していますから、知的財産法に触れることもないのではと考えています。
逆に自由に妄想していたら、先方から「このイラストが気に入ったから、リリースに使わせてほしい」と言っていただいたケースはあります。
オーディオメタバース:拡張現実と仮想現実を結ぶ音声AR空間 | 知財図鑑
元になった知財は「オーディオメタバース」という、拡張現実と仮想現実を結び付けて、いつでも誰でも交流可能な音声AR空間を形成する技術なのですが、そもそも音という見えないものにARが重なったら技術説明だけではなかなか活用例がイメージしにくい。
そこで、『知財図鑑』で「リアルな街にアーティストの演奏音源を内蔵したキューブを設置し、現実の会場からも、仮想空間からも参加できる新しいLIVEフェスを実現する」という妄想プロジェクトをイラスト化して掲載しました。
これを見たAudio Metaverse社の代表の井口さんがとても気に入ってくれ、プレスリリースにもこの「妄想プロジェクト」のイラストが使用されています。リリースの効果としても、BBCをはじめとした海外メディアからの取材がくるなど普段のリリースの何十倍も反響があったそうで、それにはイラストの引きが大きかったと分析されていました。
―それは美しい話ですね。知的財産権は独占権ですから、「第三者は無断で触ってはいけない」という考えが伝統的にあるのですが、他人が触れないからこそ権利者が「死蔵」してしまうケースが多い。
知的財産法の遵守を前提としたうえで、オープンに「知財の活用」を考えていくのは、社会全体のためにも有益ですよね。
荒井さん:もちろん権利者のそれぞれの方針とか、利害関係など難しい要素が色々とあるのですが、知財は「開発し、権利を取って終わり」じゃなくて、その先の利用がもっと進めばみんなハッピーになるのではという思いが我々にあって、オーディオメタバースの件は、結果的に理想的なコラボレーションになったのではと感じています。
知財が事業につながる「新しいライフサイクル」の構築を『知財図鑑』を通じてお手伝いできればいいなと最近は考えています。
5、これからの『知財図鑑』!~知財ハンターを盛り上げたい
―これまで色々とお話を伺ってきましたが、最後に、今後の『知財図鑑』の展開や“野望”について教えてください。
荒井さん:やりたいことはたくさんあるのですが、特に取り組みたいのは「知財ハンターの組織化」かなと。
「知財ハンター」という、世の中から「すごい知財」を発見し、世の中に新たな活用方法を提案する役割は『知財図鑑』のミッションを体現した存在と言えるもので今年、商標も登録(登録 第6503066号)しています。
そこで「知財ハンター」という肩書自体をもっと世の中で広めていきたいなと。それこそ名刺に「知財ハンター」と入れたら話のタネになるような、社会的なステータスのある名前として育てられればいいなと考えています。
―「知財ハンター」になることで、金銭的なメリットはある?
荒井さん:現状では、金銭的な見返りは設定していません。もちろん『知財図鑑』で記事を書いてもらうライターさんの業務には執筆料という形で対価をお支払いすることはありますが、知財ハンターの「すごい知財を収集し、世の中にシェアする」という基本的な役割については、金銭以外の対価を得られるような仕組みが作れないかと考えていて。
―確かに、「知財を1個紹介したら、〇〇円」みたいな形は知財ハンターにはなじまなさそうです。副業禁止の企業の方だと、参加できないという制限も出てきそうですし。
荒井さん:『知財図鑑』のデータベースというか、図鑑的な部分は運営側だけでなくても、自然に情報が集まる仕組みにできればベターとも考えていて、Wikipediaのようなユーザー参画型のコンテンツに近づけていけるといいなと思います。
会社としてのコネルや『知財図鑑』の強みは、知財という先人の知恵を土台にして、その活用法や組み合わせを自由に発想したり、プロトタイプを作って世の中に提示したりする「提案力」でもあるので、『知財図鑑』のデータベースには多種多様な知財が掲載されていても良いと考えています。
―なるほど、『知財図鑑』に掲載される知財のバリエーションを増やすためには、さまざまな分野やバックグラウンドの「知財ハンター」がいたほうが良いというロジックですね。「知財ハンター」をメジャーにしていく作戦は何かあるんでしょうか?
荒井さん:1つ考えているのは「知財ハンター」のコミュニティ化ですね。漫画『HUNTER × HUNTER』のハンター協会みたいに、「〇〇ハンター」のようなジャンルに分けるとか、活動量によって1つ星~3つ星ハンターのランクを作るとか色々とアイデアを考えています。
年内には、DAO的な要素を持った自律分散型の性格を持ったコミュニティを作るために準備中で、そこに参加してくださるアーリーメンバーの募集も予定しています。その方々にはNFTの「ハンターライセンス」のような証明書を配布したいと思っています!
―妄想を現実にしていくのが『知財図鑑』だと思うので、楽しみにしています!他にも、今年の目玉になる活動はあるでしょうか?
荒井さん:そうですね、知財図鑑代表の出村による書籍が出ます。タイトルは仮ですが、『妄想と具現』といった内容を想定しており、2022年秋発売の予定で準備を進めています。
内容は知財図鑑で行っている企業向けの「妄想ワークショップ」の創造メソッドの解説などを中心に、知財を軸に未来の新規事業を作っていくために必要な考え方や、参考になりそうな知財・妄想の解説をしています。
知財業界内の人にも、外の人にもアイデアを刺激する内容になっていますので、是非読んでみてください!
-------------
―『知財図鑑』がなぜ作られたのかに始まり、「妄想」がなぜ知財活用に有益か、知財活用のアイデアを引き出す方法、知財ハンターの組織化など、さまざまな未来に繋がる話を伺いました。
知財業界にいると、どうしても「権利化」中心に考えてしまいますが、それだと死蔵で終わってしまうケースも多いです。先人の知恵である「知財」をもっと幅広く捉え、社会全体で「活用」を考える、そのために知財関係者以外にも開かれた『知財図鑑』というデータベースが役立つという話は、とても可能性を感じました。
荒井さん、ありがとうございました!
-------------
☆『知財図鑑』 公式サイト:https://chizaizukan.com/