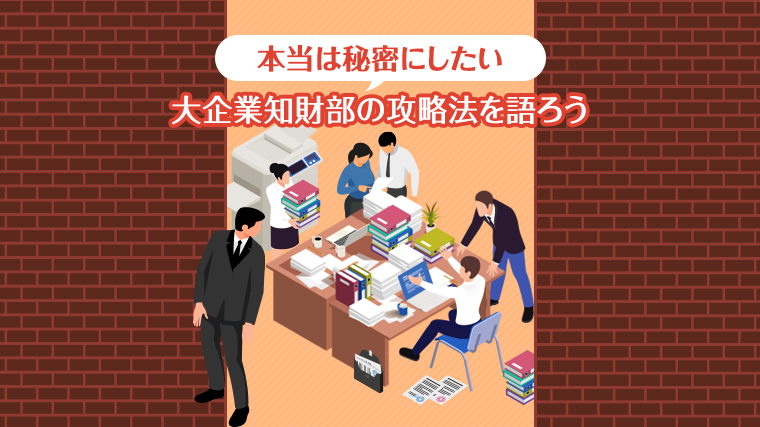小泉純一郎首相が国家戦略として「知的財産立国」を宣言したのは2002年。今から20年以上も昔です。
これは端的にいえば、製造業中心の成長モデルに限界が見えたので、新たな経済成長の柱を作ろうぜという政策であり、当時の「これからは技術・アイデア・コンテンツを重視」という視点は、今日本で言われている「クールジャパン戦略」に近い方針です。
しかし、政策に反して日本の知財人材は減少し続けています。特許庁の「特許行政年次報告書2022年版」によれば、2018年の企業における知財担当者が45,227人であるのに対し、2021年度は43,774人と3年で約4%減りました。
この43,774人は多いのか少ないのか?判断が難しいところですが、日本の企業数は約493万社(2024年9月時点)なので、平均すると約100社に1名しかいないのが知財担当という仕事です。
また、大企業の特許出願件数は、中小企業の約13倍、ベンチャー企業の約23倍という特許庁の調査報告書もありますから、「技術・知財・コンテンツ立国を目指すといいつつも、民間企業における知財人材は減少しつづけ、かつ大企業にその人材は集中している」のが日本の現実でしょう。
このような現実を打破するため、スタートアップ企業に知財活用を促したり、知財人材を呼び込もうとする試みが、特許庁の「IP BASE」や、スタートアップ知財コミュニティ「suiP」などで様々に行われており、私も個人的に応援しています。
ただ一方で、多くの知財人材が属しているはずの大企業でも人材は不足しており、「長らく中途募集していても全然採用できない」、「新人配属を会社に希望しているが、事業部優先で知財部にはまったく配属されない」、「ようやく育てた若手が、より良い環境を求めて転職してしまった」何て悩み?愚痴?を他社の方から聞くことも多いです。
スタートアップ企業の関係者が新たな知財人材をリクルートしているなら、「仕事がつまらない」とみられがちな大企業の知財部も自らの魅力を語り、知財業界に人材を呼び込む努力をしていった方が良い・・・という視点で、今回の記事を書いてみることにしました!
知財の仕事になんとなく興味がある異業種の方、大企業知財部で採用に苦戦している方、知財業界で転職を考えている方、大企業知財部で「うちの魅力って何だろう」と感じている方に読んでみていただければ嬉しいです。
ゲスト:がんばれエンタメ弁理士2号
コンテンツ系企業で勤務する社内弁理士です。前回はゲームの特許権の強さについて考察しました。勤務先は一応大企業の規模なので、自らの経験も踏まえて書いていきたいと思います。
※「大企業」の定義はさまざまにありますが、本稿では「中小企業庁による中小企業者の定義より大きい企業」を「大企業」として想定します。具体的には、製造業であれば「資本金3億円超かつ従業員数300人以上」が対象です。
目次
1、大企業知財部のメリットとは?
まずは大企業知財部の魅力をリストアップしてみます。もちろん「企業による」要素も多いですが、一般的な傾向を見ていきましょう。
<大企業知財部ならではの魅力>
① 安定した環境で働ける
・大企業ならではの安定した雇用と高水準の給与がある。また、育休・時短勤務などの制度が整っており、人員がいれば有休時に代わりに業務執行してくれる人も調整しやすく、比較的ワークライフバランスを取りやすい。
・知財業務は企業の競争力を支える重要な役割であり、社内の経験者も少ないのでリストラのリスクが比較的低い。
②大規模なプロジェクトに関われ、事業のスケールが大きい
・特許戦略・ライセンス交渉・訴訟対応など、権利化だけでない幅広い業務がある。
・グローバルでの権利網構築やM&A(企業買収)に関わる知財評価など、スケールの大きな案件が存在する企業も多い。
③社内のキャリアパスが充実
・知財専門職としての昇進(マネージャーや、企業によっては役員の道もある)や、法務・経営企画部門・事業部門への異動など、キャリアの幅が広い。
④ 事業部門との連携や役割分担が確立している
・すでに「知財戦略」や「知財体制」が確立している企業であれば、事業部門と連携する業務フローが整備されており、「なぜ知財が大事なのか」的な説明を1からする必要がない。
・役割分担が明確化されているので、「手が空いているならこれもやってほしい」的なエクストラワークが降りてくる可能性が低い。
⑤ 外部ネットワークを広げやすい
・特許庁・弁理士事務所・大学・研究機関との連携体制がすでにあり、業界団体への参加などを通じて、ネットワークを構築しやすい。
・グローバル企業であれば、海外の知財部門・法律事務所とのやり取りを通じて、国際的な知財業務のスキルを磨く機会も多い。
----
5つほど挙げてみましたが、ここで弱点も触れなければフェアではありません。メリットの背面には往々にしてデメリットもあるものです。次はそれを見ていきましょう。
2、光があれば影も・・・大企業知財部のデメリット
| メリット | 実はデメリットになる側面 |
| 安定した環境で働ける | 変化に対応しづらく、挑戦しにくい ・リスクを取らない文化があると、新しい取組み提案が通らない・すでに知財戦略が確立していると、その戦略にしたがって確立した業務(調査・権利化等)を淡々と行うことが多い・知財部の人数が多いと個人の成果が見えにくく、「出願件数」など定量的な指標で評価され手柄が立てにくい |
| 大規模プロジェクトに関われ、事業のスケールが大きい | 業務が細分化されており、個人裁量が小さい ・プロジェクト自体が大きくても業務が細分化されていると、出願・権利化・係争などの一部しか経験できない・関係部署が多数あり、他部門調整や役員への説明など意思決定に時間がかかることが多い |
| 社内のキャリアパスが充実 | 専門性が大企業に特化し、転職・独立が難しい ・知財部門内でのキャリアパスはあっても、他部門への異動は限定的な企業が多く、「知財の社内専門家」に留まりがち・多くは豊富な予算を生かした、「大規模な知財ポートフォリオ構築・管理」が業務となり、スタートアップのような「限られたリソースで最適な知財資産を構築・管理」するサバイバル能力が育たない・自ら明細書作成などの実務をやっていないと、事務所やスタートアップでの即戦力になれず、転職が難しい |
| 事業部門との連携・役割分担が確立 | 知財部門の立場が弱いと、「下請け化」しがち ・事業部の意向が強い企業であると、知財部門は下請け的な存在になり、「依頼された調査・出願をこなす社内事務所」にもなりがち・知財組織が大きいと、経営層に直接アクセスできず、事業の意思決定に関与できない |
| 外部ネットワークが広げやすい | 負荷がかかる割には、実際の業務には活かしづらい ・確かにセミナーには参加しやすく情報は得られるが、会社の方針や意思決定プロセスに縛られ、実務での実践につなげにくい・外部団体に派遣されるのは管理職以上で、一般の知財部員は特許事務所や他企業との定型的なやり取りに留まることもある |
まさに表があれば裏があるといった内容ですね。スタートアップ企業での求人は、意思決定の速さや、未整備の知財戦略・体制を1から作り上げることの楽しさを前面に出していることが多いように思います。
ToreruMediaでもsuiP(スタートアップ知財コミュニティ)のコラボ記事で、
・「知財の第一人者となる、それがスタートアップに転職する可能性」
・「スタートアップで働くとは、自分らしくあること」
・「スタートアップはRPG感」
という魅力が語られていました。安定の反対にあるスピード感や、自分の主役感・コントロール感がスタートアップ知財の魅力であり、これは確かに「大企業知財部」では薄いものだと思います。
3、大企業知財部の「デメリット克服法」
ここまで魅力・デメリットについて語ってきましたが、私自身は「職場環境が安定している」、「事業規模が大きく、知財案件の規模も大きい」、「グローバル案件の経験が積める」、「外部ネットワークに関与しやすい」というメリットを高く評価しており、大企業の知財部で10年以上勤務してきました(まあ、なんとなく転職するチャンスを逃した部分もあります)。
ただ、紹介したデメリットは確かに存在するとは感じます。そこで、デメリットを軽減するような社内での動き方をしてきました。そのような行動を認めてくれる会社だったという幸運はありましたが、他の方の参考になるかもしれませんのでTipsを紹介していきます。
① あえて知財部内の「傍流」に回る
目的:業務の守備範囲を広げ、希少性の高いスキルを身に付ける
大企業の知財部では侵害予防調査、権利化、ポートフォリオ管理といった業務はすでに定型化されていることが多いですが、あえて主流ではない業務(傍流)に手を挙げると、他のメンバーにない経験を積むことができます。
何が傍流かは企業によって異なりますが、例えば知財デューデリジェンス、侵害対応、オープンイノベーションなどは社内で定型化されておらず、自分で業務を構築するチャンスがありました。
傍流なら上手くいかなくても上から詰められることは少なく、業務の流れを構築できれば「自分の功績」と言いやすいので、実は美味しい仕事です。
もちろん、その「傍流の仕事」が社内で本当にニーズがあるかは検討し、投下するエネルギーを調整していく必要はあります。
② 部門定例会で「最近やってること発表」を行う
目的:自分の業務を可視化し、周囲からの理解度を高める
大企業では決められた業務を淡々とこなし、また報告も出願件数や経費など数字にフォーカスした内容になりがちです。そこであえて、「最近業務で工夫したこと」や「新たな発見」を自主的にフィードバックし、周囲のコメントをもらうことで、自身の業務や活動について関心を持ってもらい、協力者を集めることが有効です。
レスポンスをしてくれる人は「自分と同じ視点を持っている人」である可能性が高いですし、発表に経営・事業視点を絡めれば、「事業部への提案」に昇華もしやすく、そこまで持っていけば知財部のプレゼンス向上にも貢献できます。
人数が多い大企業の知財部では、新しい案件があったときに「あいつ、色々考えてるみたいだから声をかけてみるか」という形で機会を得ることが大切で、「面白い仕事にありつく」チャンスが広がるメリットがありました。
③ 社外での活動に「自分から」手を挙げる
目的:「義理」的な社外活動を回避し、関心が持てる外部コミュニティに時間を投下する
外部ネットワークを広げやすいのが大企業のメリットの1つと紹介しましたが、実は会社の立ち位置上、義理で誰かを派遣しなければならない社外団体もあったりします。
もちろんそのような団体でも「学び」は得られますが、義理的な参加を求められる場合、特定の個人を頼るというより「その会社の看板を持った人なら誰でも」という肩書に期待されているケースも多いです。この場合、転職してしまうとその団体で得られた人間関係はほぼ消滅、なんて勿体なさも・・。
社外活動の選択肢が複数あるならば、自分自身のキャリア・スキルアップに役立ちそうな派遣先を自ら希望し、場合によっては「ここ、新しく参加したいです」と手を挙げることで道を切り拓く、そんな動きが自らの経験を高めます。
④ お金をもらわない「副業?」をする
目的:副業禁止のルールを守りつつ、知財スキルを磨く
近年、副業OKの大企業も増えてきましたが、副業禁止の企業もまだまだあります。対策は簡単、「本業とは別に収入を得るために取り組む仕事」が副業であれば、収入を得なければ良いのです。
具体的には、会社を辞めてスタートアップに転職した同期・友人の知財相談に乗ったり、知財ブログ・記事を執筆したり、プライベートで知財関連の研究会に参加したりといった選択肢があります。
「お金を稼げないなら意味ないじゃん・・」ではなく、「経験値が上がることが報酬」と思えるかが大切です。私自身も上記の活動で得た知見が、社内での新たな業務に役立ったことが度々ありました。
⑤ 部内でメンバー・同僚を積極的に助ける
目的:組織内で信頼を得て、影響力を高める
大企業では知財部員も複数おり、業務もある程度細分化されていることから部内で連携する機会が多いです。あらかじめ自分から「何でも聞いてOK」、「手伝いしますよ」という雰囲気を作っておくことで、信頼関係ができ、結果的に自分も助けてもらいやすくなりました。
また、ナレッジ共有のために自らマニュアルを作ったり、勉強会を主催するのも有効です。結局、連携で他の人に知識を伝えなければならないなら、何度も個別に説明するより「基本マニュアル」を作っておき、それを読んでもらってから分からないところを個別に質問してもらった方が効率的です。
このような活動を通して自分自身の知識が整理され、応用業務に取り組みやすくなるだけでなく、部内で「後輩を育てられる人」と評価され、信頼度も高まります。
----
これらの工夫の共通点は「待ちの姿勢」ではなく「自ら動く」ことだと言えます。否応なしに突発イベントが降ってきて、自ら動き続けなければゲームオーバーにもなるスタートアップ知財に対し、正直、大企業の知財部は与えられた業務をこなすだけでも生活できます。
ただ、実は「降ってくる業務」も誰かが最初に作った業務であり、元々は自ら動いた人が切り拓いたものなのです。今の大企業も、かつてのスタートアップ。激動の時代だからこそ、大企業内であっても自ら動く、それで仕事の楽しさは生まれるものだと思うのです。
おわりに~企業を起点に、世界を変えよう
本記事では大企業知財部のメリット・デメリットと、デメリットを踏まえた攻略法を紹介しました。結局、攻略のコツは「自ら動く」ことに集約されますね。
ちなみにタイトルで「本当は秘密にしたい」と書いたのは、全員が同じことを実践しだすと、結局は差別化ができなくなり、また別の「差別化戦略」が必要になるよなという気持ちからだったりします。
最後に大企業で働くことの価値ですが、個人的には「体制側からのイノベーション」を最も実現しやすい場所が、やはり大企業であるからだと考えています。
いまその場で、目を上げて周囲360度をグルリと見回してみてください。目に入ってくるものの90%以上が、どこかの企業によってつくられたものだということに気づくはずです。
僕らの人生の90%は、企業によって生み出されたものを、食べたり、飲んだり、観たり、着たり、乗ったり、捻ったり、振り回したり、投げたり、叩いたり、かき鳴らしたり、弄ったり、壊したりすることに費やされています。
したがって、企業が変われば世界が変わる。世界を変えようと思うのであれば、企業を変えるのが一番手っ取り早いのです。
知財部は企業内では事業部門に比して「傍流」とみなされがちですが、実は知財戦略は「経営戦略」にも影響を与えることができたり、イノベーションの方向性を知財部門から提言することで、企業という大きな「投資・開発主体」が向かう方向をコントロールすることさえ可能だったりします。
そして大企業であるほど、社会に与える影響は比例して大きくなっていきます。
企業が社会に与えるインパクトを、知財業務という専門分野から提言・コントロールしていく。これこそが、大企業の知財部で働く最大の醍醐味なのかもしれません。