こんにちは。 ブランド弁理士®︎ の土野(@FHijino)です。
商標登録出願をしたものの、特許庁から拒絶理由通知(審査不合格の通知)を受けてしまったとき、その判定を覆して商標登録を成功に導くためのカギとなるのは意見書です。
意見書とは、「このままだと審査不合格にするつもりですよ」という特許庁審査官からの通知(拒絶理由通知)に対して、「いやいや、〇〇という理由で、この商標は登録を認めるべきですよ」と反論するための書面です。
意見書で有効な反論をするためには、ロジカルかつ客観的な主張を展開する能力に加え、商標法に関する高度な専門知識と豊富な経験が求められます。
そのため、商標のプロかどうかに関わらず、「どう書けば勝てるのか?」というコツが気になる方は多いことでしょう。
筆者は、商標を専門とする弁理士として10年以上商標実務に携わり、偉大な先輩方のご指導を受けながらたくさんの意見書を自ら書くとともに、社内外の弁理士や実務家に意見書の書き方をアドバイスする機会にも恵まれました。
また、個人的な関心と仕事上の必要性から、人の心の動きや集団力学のようなものも自分なりに学んできました。
そんな中で、商標意見書において「これが最も大切なコツだな」と考えるに至ったことがあります。
それは、商標意見書では「反論」をしてはいけないということです。
意見書は反論書面であるはずなのに、一体なぜでしょうか?
今年(2023年)の Toreru Media の年間テーマである「商標意見書」の特集記事第1弾として、このお話を書いてみたいと思います。
商標実務の話ではありますが、一方で「説得の技術」「人を動かす技術」の話でもあります。
もしご興味があれば、お付き合いいただければ幸いです。
目次
1.まずは商標意見書の “性質” を考えてみよう
商標意見書で「反論」をしてはいけないのはなぜか。
その理由を明らかにするために、まずは商標意見書に特有の “性質” を考えてみましょう。
性質1:反論の前提となる出願内容を大きく修正できない
特許と違って商標は、出願内容を後から大きく修正できないルールになっています。
たとえば、特許出願(技術的アイデアの権利取得)の場合ですと、「消しゴムがついた鉛筆」に権利がほしい!という内容で出願してNGだったときに、「角が立った消しゴムがついた鉛筆」という内容に後から修正した上で「たしかに、単に消しゴムがついた鉛筆は以前から存在したようだけど、角が立った消しゴムがついた鉛筆はこれまでなかったのだから、特許に値します」というような反論をよく行います。
これだと、審査官が「Aという内容だと特許が認められないよ」と言ったことに対して「A’ に変更すれば、認めてくれるでしょ?」と返すので、審査官の最初の判断そのものを否定することなく、前提を変更して、特許を認めさせることができます。
一方、商標登録出願の場合には、「Toreru」というネーミングに権利がほしい!という内容で出願してNGだったときに、じゃあ「Tore-ru」に変えるのでどうですか?というふうに、商標自体を後から変更することはルール上禁止されています。
そのため、審査官が「この出願内容では登録は認められないよ」と言ってきたら、基本的には、真っ向から「その判断は間違っているよ」と主張し、納得させなければ、十分な内容で商標権を獲得することはできません。
このように、商標意見書には、審査官の判断(考え)そのものに対して石を投げる形にどうしてもなってしまう、という宿命があるのです。
性質2:特許庁審査官と一対一で対峙
意見書を特許庁に提出する場面では、審査官は言い争いの当事者になります。
こう言うと当たり前に聞こえるかもしれませんが、裁判と比べると、実は意外と特徴的なことなのです。
裁判での争いは、「原告 vs 被告 ← 裁判官」という構図です。

原告と被告が言い争う当事者で、ジャッジする裁判官は第三者的な立ち位置でどちらの言い分が妥当かを判断することになります。
一方、商標意見書の場合には、「出願人 vs 審査官」という構図です。
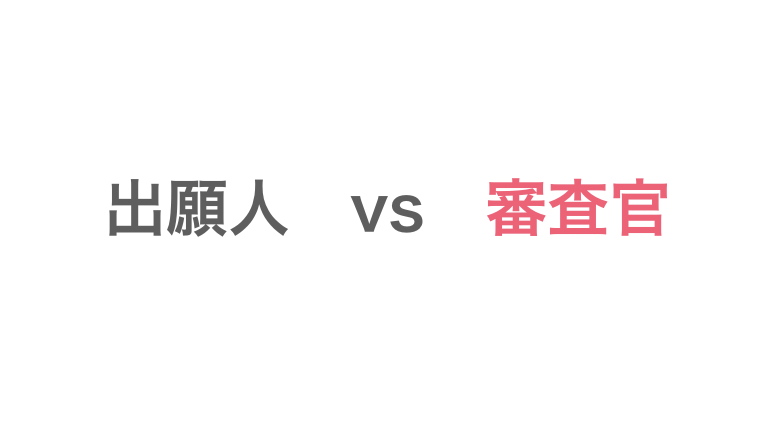
すなわち、ジャッジする審査官は言い争いの当事者であり、出願人はその審査官自身が持つ元々の見解を変えさせなければなりません。
また、審査官は基本的に1人で判断をする、という点にも留意しなければなりません。
裁判では、合議体が組まれる場合、複数(3名や5名)の裁判官がチームで判断します。複数名の意見を統合するので、異なる意見も受け入れやすい状況といえます。

一方、特許庁の審査官は1人で担当するため、基本的には1人で判断をします。出願人から意見書が提出された場面では、自分自身が一度下した判断を1人で変えることを迫られるため、心理的に、異なる意見を受け入れにくい状況に置かれているといえます。

商標意見書には、以上のような特有の性質があります。
そうすると、次のようなことが問題になってきます。
2.「反論」すると、審査官個人の知性を否定することになる
「お前の意見は間違っている」はツラい
これまで見てきたように、商標意見書では、審査官1人に対して真っ向から対立する意見をぶつける構図になります。
このような状況のとき、「反論」という姿勢で意見をぶつけてしまうと問題があります。
それは、「おまえの意見は間違っている」という伝え方は、相手の知性の否定、ともするとパーソナリティの否定として伝わりかねない、ということです。
たとえ意見を述べる側にそのつもりがなくても、です。
知性の否定やパーソナリティの否定は、受け入れ難いのが人間の心理。「人間は考える葦(あし)である。」という哲学者パスカルの有名な言葉もありますが、人間は自分の「考え」と「アイデンティティ」を結びつけてしまう傾向があります。
自分の「考え」を否定されると、あたかも自分自身の能力や人格を否定されたかのような気持ちになってしまうのです。
きっとみなさんにも、これまでの人生経験の中で思い当たることが少なからずあるのではないでしょうか。
誰もが置かれた状況下でベストを尽くしている
そもそも、審査官が「登録NGです」と判断したことは、非難されるべきようなことなのでしょうか?
もちろん、商標登録を望む出願人の立場からすれば、出願した商標にNGを出されたら、その判断をした相手を非難したくなる気持ちになることはよくわかります。その商標に強い思い入れがあれば、なおさらです。
しかしながら、この野郎!と思う前に、一つ冷静になってみたいもの。ここで思い出したいのは「根本的な帰属の誤り」という言葉です。
「根本的な帰属の誤り」(Fundamental attribution error)とは心理学用語で、人間は、相手が何かしたときに、その原因を「状況」ではなく「その人自身」に見出してしまう傾向(バイアス)がある、ということを示す言葉・概念です。
要するに、人は本能的に「状況のせい」ではなく『その人のせい』と考えがちである、ということです。
(ちなみに、自分がやったことに対しては、「状況のおかげ」ではなく『自分のおかげ』と考えてしまうバイアスがあります。耳が痛い。。。)
これは、意見書を書こうとする場面でも当てはまります。
審査官が今回「登録NG」と言ってきたのも、「審査官の判断力」ではなく、実は『審査官が置かれた状況』によるものが大きいかもしれません。
『審査官が置かれた状況』に目を向けると、たとえば、こんな事情があるかもしれません。
- 特許庁内の統一ガイドラインである「商標審査基準」に従わなければいけない立場
- 産業界(出願人側の立場の人たち)からはいつも「迅速な審査」が要請されている一方、出願件数は多く、日々多くの審査をこなさなければならない
- 現実的にアクセスできる限られた情報に基づいて判断しなければならない
- 「迷ったら登録NGを出しておこう。安易に登録OKを出したら、特許庁(国)を炎上させてしまうかも・・・」というプレッシャー
このように、一事業者である出願人と、公的なジャッジをする審査官とでは、持っている情報と置かれた立場(すなわち状況)は全く異なります。
このような前提を考慮に入れず、ただ相手(審査官)の考えを否定するのでは、相手もなかなか受け入れがたいものでしょう。
すでに述べたように、意見書の場面では審査官と一対一で対峙することになるため、審査官が自身の考えを変えることに対する「心理的ハードル」を下げてあげることが、こちらの話を聞いてもらうための大きなカギになります。
「誰もが置かれた状況下でベストを尽くしている」
この前提に立って、意見書を書くことが大切です。
3.通りやすい意見書とは?「反論」ではなく『協力者』として振る舞おう
商標意見書を「反論」の姿勢で書いてはいけないとしたら、どのようにすればよいのでしょうか?
まず重要なのは、「審査官は敵」というマインドセットを変えることです。
審査官は「敵」ではありません。
出願人が「妥当な審査を受けたい」と思っているように、審査官もまた「妥当な審査をしたい」と願っているのです。
審査官を「敵」ではなく、同じ目標(妥当な審査)を持つ『協力者』として見る。
同時に、自分(出願人)もまた審査官の『協力者』として振る舞う。
このような姿勢に変えることが大切です。
通りやすい意見書の書き方
このようなマインドセットを持った上で、以下のような意見書の書き方をすると、通りやすい意見書になります。
ポイント1:意見の内容
意見の内容は、審査官による「妥当な審査」を助けるような『新たな事実や視点』を教えてあげることに注力することが大切です。
『新たな事実や視点』とは、たとえば次のようなものです。
- 審査官がまだ知らないと思われる(拒絶理由通知書で挙げてこなかった)事実
- 一般論(教科書的判断)ではなく「本件事案だからこそ」の見方
それぞれ、具体例を挙げてみましょう。
<①の具体例>
- 商標『フィットジェル』を指定商品「化粧品」について登録出願した。
- 審査官は、『フィットジェル』の語が「肌にフィットするジェル状の化粧品」であることを説明する語(記述的な語)として使用されている事例を1件挙げて、「この言葉は単に商品の性質を説明する一般用語的なものなので登録NG」という判断をした(拒絶理由通知をした)。
- これに対し出願人は、意見書で「実は、『フィットジェル』の語が商標的に(造語として)使用されている例が他に5件ほど存在しますよ」と指摘した。
<②の具体例>
- 商標『カナサン』を沖縄で販売される商品について登録出願した。
- 審査官は、『カナサ』という先行商標の存在を挙げ「音で聴いたときに末尾の「ン」の有無しか違わないから紛らわしい。この商標と類似するから登録NG」という判断をした(拒絶理由通知をした)。
- これに対し出願人は、意見書で「実は、『カナサ』と『カナサン』はともに沖縄方言で、それぞれ「愛」と「愛している」を意味する言葉です。この発音の違いを聴き分けて区別できなければ日常生活に大きな支障が出るけど、現にその言葉が使われています。つまり両者は十分に聴き分けできると考えてよいのではないでしょうか?」と指摘した。
このような『新たな事実や視点』を中心に意見を展開すれば、その事実や視点を知らない状態で下した審査官の判断(力)を否定することなく、新しい「判断の前提」を審査官に与えてあげることができます。
これにより、
“最初の判断が間違っていたのは、審査官殿の考え方が悪いからではありません。ただ「前提A」で判断してしまったからに過ぎません。ここで「前提B」で改めて考えていただければ、私(出願人)と同じ意見にならないでしょうか?”
という形で、審査官に再考を促すことができるのです。
ポイント2:文章のトーン
意見の内容の実質を上記のようにするとともに、文章全体のトーン(書き振り・文脈)も、以下の「OK例」のようにできると、より審査官にとって受け入れやすいものになるでしょう。
× NG例:あなたの判断は間違っている。私の意見が正しい。なので、考えを改めてください。
○ OK例:Aを前提にお考えであれば、そのご判断にも無理はありません。この商標の登録を許せば、△△という点がご懸念点だったのでしょう。審査官殿の立場からすればごもっともです。しかしながら、Bという前提であればどうでしょう?このように考えれば、登録を認めても、△△のような懸念はないかと思います。
NG例とOK例の違いがわかるでしょうか。NG例はストレートに審査官の判断を否定し、考えを変えさせようとしています。一方OK例ではいったん審査官が「なぜ拒絶という結論に達したか」に共感を示しつつ、それを出発点として新しい事実や視点を提供し、登録を認めても良い理由を示しています。
一見、審査官の拒絶理由に共感することは弱腰であり、審査官の判断を認めてしまって不利になるように感じられるかもしれません。しかし、現実はその反対です。審査官には「拒絶理由を出した」登録を認めるべきではない懸念点が必ずあり、その懸念が払拭されない限り登録を認めてくれることはありません。
そう考えるといったん懸念点をありのままに認め、その懸念を新たな事実・視点により払拭することこそが、審査官に自発的に判断を変えてもらう「近道」になるのです。
ポイント3:文体
ポイント2と重なりますが、これまでお話ししてきた考え方を踏まえると、意見書の文体は、いかにも「反論書」や「法律文書」らしいものというよりも、むしろ審査官への「手紙」のつもりで書くくらいの方がちょうど良い、と筆者は考えています。
そのため、できるだけ丁寧を心がけ(冗長になる必要はありません。丁寧と簡潔は相反しないものです)、「ですます調」で書く方が、心理的に受け入れられやすい意見書になりそうです。
(ちなみに、弁理士の中でも「である調」派と「ですます調」派がいるようです。筆者はここまで述べてきた理由から「ですます調」で書いていますが、通常はほとんど趣味の範疇で、どちらかによって意見書の成功率が変わることはない、とみんな信じているかと思います。が、実際のところはどうなのでしょう。もちろん語尾よりも意見の内容が圧倒的に重要なのは間違いありませんが…。 “「である調」か「ですます調」か問題” については、いずれ Toreru Media でも改めて考察することがあるかもしれません)
おわりに
「商標意見書」が Toreru Media の2023年年間テーマとなったのをいいことに、商標意見書で最も重要だな~と最近考えていたことを書かせていただきました。いかがでしたでしょうか?
商標の登録を認めるか・認めないかの「番人」であるが故に、なにかと「敵」として見られてしまいがちな特許庁の審査官。
ですが、当然ながら審査官もひとりの「人間」であり、意見書も一種の「テキストコミニュケーション」です。
「商標登録」という特殊なフィールドであっても、人間心理を踏まえた立ち振る舞いが、ものごとの成否を分けることには変わりはないのだと思います。
もし本記事をお読みいただいた方が、商標意見書に対して新しい視点を感じてもらえたのなら、とても嬉しく思います。
