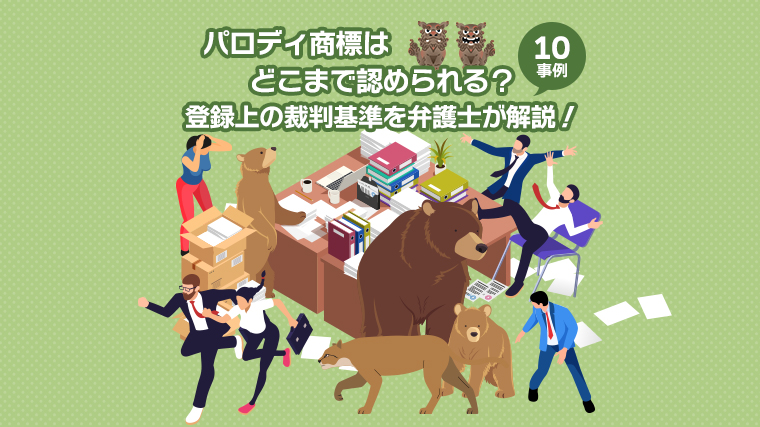「フランクミュラー」ならぬ「フランク三浦」等、著名商標を想起させるようないわゆる「パロディ商標」は巷にあふれています。
パロディ商標はユニークで見ていて面白いですが、まさに著名商標にフリーライドするものであり、商標法上の問題はないのか?という点が気になるところです。実際に「パロディされた本家」の商標権者が、パロディ商標を登録させまいとして異議申立を行うケースも複数見られます。
そこで、本記事では、商標登録にあたってパロディ商標の有効性が争われた事案を10件紹介し、そこから判断を分けたポイントを抽出・解説します。
本記事を通して、パロディ商標に対する特許庁や裁判所の判断基準を学んでいきましょう。
目次
- 1. 前提:パロディ商標の論点は?
- 2. パロディ商標が問題となった事件10選
- 2.1. パロディ側が勝利した事件
- 2.2. 本家側が勝利した事件
- 事例④ ランボルギーニ vs ランボルミーニ事件(知財高判平成24.5.31)
- 事例⑤ PUMA vs SHI-SA〔図形のみ〕事件(知財高判平成31.3.26)
- 事例⑥ PUMA vs KUMA事件(知財高判平成25.6.27)
- 事例⑦ Champion vs Nyanpion事件(特許庁無効審決令和6.11.20(無効2022-890045))
- 事例⑧ LACOSTE vs OCOSITE事件(特許庁異議決定令和4・2・18(全部異議020-900312))
- 事例⑨ BOSS vs BOZU事件(特許庁異議決定平成10・10・27(全部異議平成10-090851))
- 事例⑩ 東京ウォーカー vs 函館ウォーカーズマニュアル事件(特許庁無効審決平成22・7・28(無効2009-890123))
<はじめに>
- フランク三浦事件における「フランクミュラー」など、パロディの元ネタとなっている著名商標を、本記事では「本家」と呼ぶことがあります。
- 本記事で紹介する判例等は、「パロディ商標が商標登録され、本家がその有効性を争った事案」、すなわち、パロディ商標の登録の場面におけるものであって、いわゆる侵害訴訟は含まれておりません。
1. 前提:パロディ商標の論点は?
具体的な事案の紹介に入る前に、「パロディ商標の論点」として、どんな基準で登録の可否が判断されるのか?前提となる条文と論点を簡単に解説します。
1.1. 著名商標との類似
そもそもパロディ商標は、本家を想起させる点に本質がありますので、本来的に本家商標と類似するものです。
そのため、パロディ商標の効力を争う(つまり登録させたくない)本家側からは、本家商標との類似性を理由に、不登録事由として、商標法4条1項11号、10号、19号該当性が主張されることが多いです。これらの条文に該当すれば、登録は認められません。
※以下、4条1項の条文を示す場合には、号数のみを示します。
1.1.2. 11号(先願の登録商標と類似する商標)
11号「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務・・・又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」
他人の登録商標との類似性を理由とする不登録事由で、本家側としてはまず最初に検討するベーシックな条文です。
1.1.3. 10号(周知商標と類似する商標)
10号「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて,その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」
登録商標との類似性は11号の守備範囲ですので、10号は主として「未登録」の周知商標との類似性を問題にする不登録事由です。
未登録であっても、周知商標については、混同防止等の利益を保護しようとするのが10号の趣旨です。これに該当すれば、あらかじめ本家商標を登録していなくても、パロディ商標の登録を阻止することができるため、本家側としては重要な条文です。
1.1.4 同項19号(不正目的使用)
19号「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)」
19号は、登録/未登録を問わず、他人の周知商標と類似する商標を不正目的で使用する場合に不登録事由とする条文です。
パロディ商標は、本家商標を意識して似せていることは明らかであるため、本家側からは、この不正目的が主張されることもあります。
1.2. 著名商標との混同(15号)
15号「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)」
著名商標へのただ乗り(フリーライド)及び当該表示の希釈化(ダイリュージョン)を防止することを趣旨とする不登録事由であり、これも本家側から主張されることが多い条項です。
15号の要件である「混同を生ずるおそれ」の考慮要素を、最高裁(最判平成12.7.11〔レールデュタン事件〕)は以下のとおり示しています。
- 当該商標と他人の表示との類似性の程度
- 他人の表示の周知著名性及び独創性の程度
- 当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の関連性の程度
- 取引者及び需要者の共通性その他取引の実情
このように、類似性以外の要素も考慮して混同のおそれが判断されるため、本家側としては、10号や11号における類似性が認められなかったとしても、15号を主張する実益があります。
1.3. 公序良俗違反(7号)
7号「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」
適用される場面は限られていますが、パロディ商標が非道徳的、卑猥な場合等に適用される可能性があります(パロディ事案での適用事例として、知財高判令和4.5.25)。
1.4. 有効・無効を分ける主戦場は「類似性」
ここまで、パロディ商標の有効性に関する論点を概観しましたが、11号、10号、19号は、他の商標との類似性を前提とする不登録事由であり、15号の判断においても類似性は重要な考慮要素です。
そのため、パロディ商標の有効性に関する争いの主戦場はやはり「類似性」です。
そして、商標の類似性は、外観(見た目)、観念(連想されるイメージ)、称呼(呼び方)の共通性を考慮して判断されるというのが、特許庁の審査基準でも裁判においても確立した考え方です。
以上の前提知識を念頭に置いて、次は実際の事件を見ていきましょう!
2. パロディ商標が問題となった事件10選
ここからは、パロディ側が勝利した事件と、本家側が勝利した事件とに分けて、判例等における判断の概要を簡潔に解説していきます。
双方の商標を対比して示す場合、いずれも、左側が本家、右側がパロディです。
2.1. パロディ側が勝利した事件
事例① フランクミュラー vs フランク三浦事件(知財高判平成28.4.12)
〔裁判所の判断の要約〕
- 「フランクミュラー」と「フランクミウラ」は語感が紛らわしく、称呼が類似する。
- しかし、本家は「黒色の欧文字」、パロディは「手書き風のカタカナと漢字」から構成されており、外観は明確に区別される。
- また、本家からは海外の高級ブランドという観念が生じる一方、パロディからは「フランク三浦」という名前を用いる人物という観念が生じ、観念においても大きく相違する。
- 本家商品の価格帯(多くが100万円を超える)と、パロディ商品の価格帯(4,000円~6,000円)価格帯が異なり、需要者が双方の商品を混同するとは到底考えられない。
結論:10号、11号、15号、19号には該当しない。
〔コメント〕
手書き風書体が勝利のポイントでしょう。
類似性という観点からは、やはり外観の大きな相違が重視されています。パロディ側が手書き文字であるというのも、外観の相違に大きく影響を与えているといえるでしょう。
さらに15号の混同のおそれの認定において、価格帯、指向性の相違に言及されている点も参考になります。
事例② PUMA vs SHI-SA〔図形と文字〕事件(知財高判平成21.2.10)
〔裁判所の判断の要約〕
- 文字部分は、アルファベットの「A」以外全て相違する。動物の部分も、パロディ側の方が頭が大きく、歯のようなものが描かれている等、相違点あり。
- パロディ側の「OKINAWAN ORIGINAL GUARDIAN SHISHI-DOG」の文字からは、沖縄の伝統的な「シーサー」が観念され、本家からは、動物の「ピューマ」、「PUMA」ブランドの観念が生じる。観念は相違する。
- 称呼も、「プーマ」と「シーサ」で異なる。
結論:11号には該当しない。
〔コメント〕
文字部分の大きな違いが、勝利のポイントですね。
沖縄のお土産屋さんで見かけるパロディ商標です。
ぱっと見の外観はかなり似通っているようにも思えますが、パロディの文字部分が本家との相違点を印象付けています。
ちなみに、文字部分は「SHISHI-DOG」=シーシドッグとなっていますが、シーサーは地域によっては「シーシ」とも呼ばれるそうです。
事例③ ローリングストーンズ vs Acid Black Cherry事件(知財高判平成22.1.13)
〔裁判所の判断の要約〕
- 色や形等の全体的な構成は共通しているが、本家は斜め方向から見た立体的な図形であるのに対し、パロディは正面から見た平面的な図形である点で異なる。また、パロディ側にある3本の黒色の図形や、右上の黒い丸については、本家と異なる。
- 称呼・観念においても共通性はない。
- 本家商標は、英国のロックバンド「ローリングストーンズ」に関する商品等を示すものとして、音楽関係の取引者・需要者の間で周知・著名である。しかも、需要者である音楽ファンは、音楽CDを購入する際や、ライブに参加しようとする際、自分の好みのアーティストのものであるかどうか、注意深く観察するのが一般的であり、混同は生じにくい。
結論:15号には該当しない。
〔コメント〕
ポイントは、音楽ファンにとっての識別力です。
本家は「ローリングストーンズ」、パロディは「Acid Black Cherry」が使用する商標であり、いずれもロックバンドという点で共通しています。
しかし、外観の大きな相違に加え、嗜好性が高いという音楽の特徴を理由として、混同のおそれなしと結論付けており、説得力がある判決です。
たしかに、「ロゴが似てるから違うアーティストのライブ会場に来ちゃったよ!」なんて人はいないでしょう・・・。
2.2. 本家側が勝利した事件
事例④ ランボルギーニ vs ランボルミーニ事件(知財高判平成24.5.31)
〔裁判所の判断の要約〕
- 本家「ランボルギーニ」とパロディ「ランボルミーニ」の称呼は、一文字しか異なっておらず、しかも、相違する音(ギとミ)は、母音構成を共通する近似音である。
- パロディ商標の字体に特徴がある点、図形も付加されている点で外観において若干の相違があるものの、全体として類似する。
- パロディ側は、本家が製造・販売する自動車を模したカスタムバギーを製造・販売しており、混同のおそれがある。
- パロディ側は、本家商標が世界的に著名な自動車メーカーであること、本家との類似性を認識しながら商標登録を行い、しかも、本家と同様の商品を製造・販売していることから、「不正の目的」が認められる。
結論:10号、15号、19号に該当する。
〔コメント〕
見た目は結構違いますが、意外にも?本家側が勝利しました。「ランボルギーニ」の著名性も判断に影響しています。
ただ、本訴訟では、被告(パロディ側)は裁判所に出頭せず、何らの反論もせずに判決に至っています。
本判決は、称呼の共通性を重視して商標の類似性を認めていますが、一見して、外観における相違点は無視できません。
また、混同のおそれについては、双方が同種の商品を販売していることを認定していますが、それ以上に、価格帯の差等には言及されていません。
もし、これらの事情について被告(パロディ側)が反論をしていれば、判断の内容は変わったかもしれませんね。
事例⑤ PUMA vs SHI-SA〔図形のみ〕事件(知財高判平成31.3.26)
〔裁判所の判断の要約〕
- 四足動物が右から左に向かって跳び上がる姿を側面から見た姿でシルエット風に描かれているという外観は共通している。
- パロディの歯のような模様や首回りの飾りのような模様等の点で異なるが、全体に占める面積は比較的小さい。
- 本家からは、プーマブランドの観念とプーマの称呼が生じるが、パロディからは何らの観念、称呼も生じない。このように、観念、称呼が共通とはいえないが、パロディから何らかの観念、称呼が生じ、これが本家と類似しない場合と比較して、その違いがより明確であるということはできない。
- パロディは「Tシャツ、帽子」を指定商品としているところ、本家のプーマブランドの商品としても、Tシャツ、帽子が存在するため、取引者、需要者が共通するといえる。
結論:15号に該当する。
〔コメント〕
図形のみの比較では、混同ありの判断です。
先ほど紹介した図形と文字が含まれている「PUMA」事件では、非類似の結論となっていましたが、図形のみの本件では混同のおそれを認めて本家側の勝利となっています。
やはり、図形自体の類似性は高いため、図形以外の文字部分で違いを明確しないと、混同のおそれを否定することは難しいといえるでしょう。
また、「パロディからは何らの観念、称呼が生じない」と認定し、違いが明確であるとはいえないと認定した点も特徴的です。
すなわち、パロディから「シーサー」の観念や称呼が生じていれば、本家の「プーマ」との違いはより明確となり、結論は変わっていたかもしれません。
事例⑥ PUMA vs KUMA事件(知財高判平成25.6.27)
〔裁判所の判断の要約〕
- 四足動物が文字部分に向かっている様子を側面からシルエット風に描いたという点で共通する。
- 文字部分は「K」と「P」が相違するのみであり、縦線が太く、横線が細い等の書体の特徴が酷似している。
- 各商標が付されるズボン、Tシャツ、帽子等の商品は、ブランドについて詳細な知識を持たず、商品の選択・購入に際して払う注意力が高いとはいえない一般消費者を需要者とする点でも共通する。
- パロディ側は、ウェブサイト上に「PUMAではありません」「PUMAのロゴに似ているような似ていないような。」等と記載していることや、商品販売について著作権侵害の警告を受けたこともあること等からすれば、公序良俗違反も認められる。
結論:15号、7号に該当する。
〔コメント〕
3つ目の「PUMA」事件、今度はシーサーではなく、クマが登場です。
この事件、文字部分の共通性は高い一方、動物部分の相違は大きいといえるのではないでしょうか。
裁判所は、ピューマとクマを「四足動物」で一括りにしていますが、パロディ商標のクマは二足で立っていますし、シルエットもクマらしくずっしりしており、動物部分の印象は結構異なるように思います。全体を比較すると、類似・非類似どちらの判断に転んでもおかしくない事例だったと思います。
他方、混同のおそれの観点からは、他の判例と同様、需要者層の特徴にも言及されており、本件では、需要者が「一般消費者」であることから、混同のおそれを肯定する方向で考慮されています。
この点は、嗜好性の高さを理由として混同のおそれを否定した、前記「ローリングストーンズ vs Acid Black Cherry事件」と対照的です。
また、本件では、7号(公序良俗違反)が認定されている点も特徴的です。
商標自体が非道徳的、卑猥というわけではありませんが、パロディ側の商品販売サイトにて、明らかに本家を意識したような記載があったこと等の事情が考慮され、7号の認定がなされています。
このように商標自体の類似・非類似だけでなく、パロディ側がどのように使用していたか等の要素も勘案して、裁判所の判断は下されます。
事例⑦ Champion vs Nyanpion事件(特許庁無効審決令和6.11.20(無効2022-890045))
特許庁無効審決令和6.11.20(無効2022-890045)より
〔特許庁の判断の要約〕
- 図形部分は、「開口部を有する青色太線で描かれた楕円形の内部を3つに分けて中央を青色で塗りつぶしている」等の特徴が共通している。
- 他方で、パロディ商標には猫の顔や耳が描かれているという点で相違するが、前記共通点(①)は、著名な本家商標の特徴と共通しているのであって、このような共通点の方が需要者に対して強い印象を与える。
- 本家からは「チャンピオン」、パロディからは「ニャンピオン」の称呼が生じるところ、相違点は「チャ」と「ニャ」のみであり、母音を共通にする。
- 取引者・需要者は共通である。
結論:15号に該当する。
〔コメント〕
今回一番かわいいパロディです。
たしかに図形部分は、「C」マークの開口部分が左右逆になっていますが、そのような相違点よりも、全体的な構成の共通性が重視されています。
また、称呼の共通性の点では、相違する音があっても母音を共通にする場合には、類似性を肯定する方向で認定されており、この点は前記「ランボルギーニ vs ランボルミーニ事件」と同様です。
なお、本無効審決に先立ち、本家側は登録異議申立ても行っており、同異議申立てにおいては、パロディ側勝利(登録維持)の結論となっています(異議2021-900230)。
このように、特許庁の判断が、無効審決と異議申立てで異なっている点も特徴的です。
事例⑧ LACOSTE vs OCOSITE事件(特許庁異議決定令和4・2・18(全部異議020-900312))
特許庁異議決定令和4・2・18(全部異議020-900312)より
〔特許庁の判断の要約〕
- ワニの向きや足の数等で相違点はあるが、主要な特徴を同一としており、類似性の程度は高い。
- 取引者、需要者を共通にする。
- 不正な目的や公序良俗違反性はなく、19号、7号には該当しない。
結論:15号に該当する。
〔コメント〕
これはアイデア賞ですね。ただ、著名商標との混同が認定され、登録は認められませんでした。
判断ではやはり、図形部分の共通性が高い点が考慮されています。
しかも、特許庁の判断の中では明示的に認定されてはいませんが、本家側は、ワニの図形部分がデッドコピーといえるほど類似していると主張しています。
たしかに、ワニの顔の部分や背中の部分はほぼ同一であり、本家商標をコピーして、編集を加えたようにも見えます。
事例⑨ BOSS vs BOZU事件(特許庁異議決定平成10・10・27(全部異議平成10-090851))
特許庁異議決定平成10・10・27(全部異議平成10-090851)より
〔特許庁の判断の要約〕
- パロディ商標は、本家商標の「BOSS」を「BOZU」に置き換えたにすぎず、図形部分は頭髪を除けばほぼ同一である。
- 本家商標を付した商品の販売数量は極めて多く、本家商標は取引者、需要者間に広く認識されるに至った。
結論:15号に該当する。
〔コメント〕
坊主も似合う、この男。
ラコステ事件同様、パロディロゴはほぼデッドコピーに近いような事案であり、類似性の程度は相当高いといえるでしょう。
なお、このおじさん、「働く男の相棒」を表現したオリジナルキャラクターで、サントリー内部の方がデザインしたそうです(「BOSS缶に描かれたダンディな男性は誰? サントリーに聞いてみた」より)。
事例⑩ 東京ウォーカー vs 函館ウォーカーズマニュアル事件(特許庁無効審決平成22・7・28(無効2009-890123))
特許庁無効審決平成22・7・28(無効2009-890123)
※ パロディ側が上記「函館ウォーカーズマニュアル」です。
※ 本家側は「東京ウォーカー」等、「都市・地域名」と「ウォーカー」を結合させた商標を用いて雑誌等を販売しています。
〔特許庁の判断の要約〕
- 「函館ウォーカーズマニュアル」も、本家である東京ウォーカーと同様、地域名+ウォーカー(ズ)の組み合わせである。
- ウォーカーとウォーカーズは、語尾の「ズ」の有無で異なるが、日本において複数、単数の違いは明確に区別して捉えない場合が多く、比較的聴取され難い語尾に位置することからすれば、「ズ」の有無が称呼に及ぼす影響は小さい。
- 「マニュアル」の有無でも異なるが、「マニュアル」とは手引書という意味であり、指定商品である「雑誌」との関係からすれば、識別標識としての機能はほとんどない。
- 函館ウォーカーズマニュアルは、東京ウォーカー等のシリーズの一つとして認識されるおそれがある。
結論:15号に該当する。
〔コメント〕
「シリーズ物」の勝利といえます。
有名な雑誌「東京ウォーカー」の事件です。
商標の比較においては、「ズ」の意味合いや商標中の位置(語尾であること)、「マニュアル」という言葉の指定商品との関係における意味合いに着目している点が興味深く、説得的な判断内容です。
また、本家が東京ウォーカーをはじめとして、関西ウォーカーや九州ウォーカー等の「都市・地域名」+「ウォーカー」から成る商標を多数使用しており、パロディ商標がそのシリーズ物の1つとして認識される可能性が高いという点も判断で重要な要素となりました。
3. 10事例から学べる、パロディ商標の基準とは?
3.1. 判断を分けたポイント
今回紹介した判例等から、パロディ商標が無効になるか否かの判断のポイントをまとめてみます。
3.2.1. パロディ特有の文字が付加されているか否か
事例②「PUMA vs SHI-SA」〔図形と文字〕事件で見たように、パロディ側に特有の文字があれば、その部分から特有の観念、称呼が生まれることとなり、本家との違いがより明確になります。
他方、事例⑥ 「PUMA vs KUMA事件」では、パロディ商標の上部に小さく「KUMA」とのゴシック体文字が付加されていましたが、裁判所は「目立たない位置にあることや表示が小さいこと等により看者の印象に残らない。」と認定し、これをもって類似性を否定するほどのものではないとされています。
パロディ側に付加されている文字の数や位置、意味合いがポイントといえるでしょう。
3.2.2. 本家のデッドコピーか否か
当然ですが、本家商標のデッドコピー(コピペ)に近いようなものは、類似性においてほぼ反論の余地なしという状況になってしまう場合もあります。程度によっては著作権侵害にもなり得ます。
明確に認定されたものではありませんが、「事例⑧ LACOSTE vs OCOSITE事件」、「事例⑨ BOSS vs BOZU事件」の各商標を比較すると、デッドコピーに近い部分があるといえるでしょう。
3.2.3. 需要者の共通性、性質
「事例⑦ Champion vs Nyanpion事件」や「事例⑧ LACOSTE vs OCOSITE事件」等では、混同のおそれを肯定する要素として、需要者の共通性に言及されています。
また、「商品の選択・購入の際に払う注意力の程度」という意味で、需要者層の性質に言及する判例等もあります。特に、高級でない一般衣料品等については、需要者層の性質から混同のおそれが肯定されやすいといえるでしょう。
この点に関しては、「事例① フランクミュラー vs フランク三浦事件」では混同のおそれを否定する方向で、「事例⑥ PUMA vs KUMA事件」では混同のおそれを肯定する方向で考慮されており、判断を分ける重要なポイントです。
「事例③ ローリングストーンズ vs Acid Black Cherry事件」では、需要者である音楽ファンの性質に言及し、混同のおそれを否定しています。
3.2.4. 相違している文字の数等
商標中の文字部分は、称呼、外観に影響を及ぼすため、文字部分の相違も重要です。特に、相違している文字の数、相違している文字の母音構成の一致の有無、全体の発音の紛らわしさが重視されています。
特に、「事例④ ランボルギーニ vs ランボルミーニ事件」、「事例⑦ Champion vs Nyanpion事件」では、相違する音が1つのみであり、その相違する音の母音構成が同一である点が、称呼の共通性の認定において重要なポイントとなっています。
3.2. さいごに
今回紹介した10個の事例をもとに、パロディ商標の登録可否の判断基準を表にまとめてみました。
各事例はいずれも、商標法4条1項各号への該当性を淡々と検討しており、「パロディであるから」という理由のみで、パロディ側に有利にも不利にも特別扱いはされていません。
フランク三浦事件でも、裁判所は以下のとおり述べています。
「本件商標が商標法4条1項15号に該当するか否かは,飽くまで本件商標が同号所定の要件を満たすかどうかによって判断されるべきものであり,原告商品が被告商品のパロディに該当するか否かによって判断されるものではない。」
知財高判平成28.4.12より
海外では、商標法・著作権法の分野で、パロディに特別の扱い、すなわち表現の自由・批評精神の表れなどという観点から、積極的に価値を認めているところもありますが、少なくとも日本では、パロディというだけで特別扱いはされません。
日本の商標登録の現場では、パロディに「特別扱い」は無く、あくまでも商標法の枠組みの中で決着が付いているということを、本記事であらためて知っていただければと思います。