商標登録が最もひしめき合う分野の一つが「化粧品」分野です。
比較的進出しやすい分野ということもあり、「化粧品」分野で商標登録をしようとする人はたくさんいます。
この記事では、このように多くの方の関心の高い「化粧品」の商標登録に特有のポイントを解説していきます。
化粧品分野で商標権を取りたいときに選ぶべき「区分」や、化粧品分野ならではの注意点などを、専門家の経験を踏まえながらまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
目次
1. 商標の化粧品の重要な区分
商標登録をするときの化粧品の区分は「3類」です。
化粧品について商標登録するには、区分を「3類」とし、指定商品を「化粧品」と書けばOKです。
しかし、指定商品を「化粧品」と書いたときに、どのような商品までが権利範囲として含まれるのでしょうか?パッとはわからないですよね。
商標の指定商品の表現は、日常で使う意味合いと少しズレていることがよくあります。「普通は石けんも化粧品のカテゴリーに入るでしょ」と思っても、商標の世界ではそうとは限りません。
ここがズレていると、「権利を取ったつもりが取れていない」という事態になってしまいますので、注意が必要です。
そのため、3類の「化粧品」についても、この範囲に含まれる商品を確認しておきましょう。
「化粧品」という指定商品に含まれるものの例
- おしろい
- 化粧水
- 化粧用クリーム
- クレンジングクリーム,ひげそり用クリーム,日焼け止めクリーム,ファウンデーションクリーム,リップクリーム
- 口紅
- ヘアートリートメント
- 香水類,オーデコロン,香水,固形香水,練り香,粉末香水
- アイシャドウ
- あぶらとり紙
これは一例ですので、もっと知りたい方は商標の区分 3類をご覧ください。
なお、3類では「化粧品」以外にも、たとえば以下のような商品も指定することができます。これらは、化粧品に関連するものであり、日常的には「化粧品」という概念に含まれていると考えられているものもありそうです。
- せっけん類
- 歯磨き
- 香料
- 薫料
- つけづめ
- つけまつ毛
たとえば、先ほど例に挙げた「石けん」は、商標の世界では「化粧品」には含まれません。もし「石けん」についても商標権を取りたい場合は、「化粧品」とは別に「せっけん類」と書いておく必要があります。なお、この「せっけん類」には、「シャンプー」が含まれます。化粧品について商標登録するなら、これについても権利を取っておく必要性が高いと言えるでしょう。
このように、これらの商品は「化粧品」には含まれないものとして扱われますので、3類で商標登録するときには、合わせて書いておくようにするのがおすすめです。
2. 商標の化粧品のその他の区分
化粧品について商標登録する場合、メインとなる「3類」のほかにも、たとえば以下のような区分でも登録をしておくことを検討するとよいでしょう。
- 35類
- 化粧品の小売
35類には、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」というサービス(役務)があります。
これは、たとえばコンビニエンスストアやセレクトショップのように、いろいろなメーカーの商品を小売店や卸売店として販売する事業を行う場合に登録すべき指定役務です。また、メーカーとして化粧品等を製造し小売店等に出荷するだけでなく、自らブランドショップを開いて消費者に直接販売するような場合にも、登録しておいた方が望ましいです。
3類との違いが理解しにくいかもしれませんが、簡単に言うと、①商品自体のブランド名としてその商標を使用する場合は3類、②その商品を販売するショップ名(ECサイト名を含む)にその商標を使用する場合は35類、というように理解していただければ、ひとまずよいと思います。
- 5類
- サプリメント
- 薬剤
5類の「サプリメント」や「薬剤」も登録しておいた方がいい場合が多いです。
「サプリメント」については、化粧品を扱う場合、美容や健康を提供するという共通点があるため、サプリメントへも商品展開することが少なくないためです。
「薬剤」については、取り扱う商品によっては3類「化粧品」と5類「薬剤」のどちらに該当するか曖昧なものがあるからです。
たとえば、育毛を促す効果が期待できる液状商品の場合、「育毛効果のある頭髪用化粧水」は3類ですが、「育毛剤」は5類とされています。医療目的で使われるような性質のものほど5類に近づくのですが、実際の商品について考えると、このボーダーがはっきりしないようなものもあるため、3類だけで守れている、5類だけで守れている、と断言できない場合が多いのです。
また、当初は完全に3類に該当するような商品しか扱っていなかったとしても、事業展開によって後により薬効の高い商品を扱う可能性も十分あり得るかと思います。
そのため、3類と5類は合わせて登録しておくとよい場合が多いと言えます。
- 21類
- 化粧用具
21類に属する「化粧用具」には、たとえば「くし」「化粧用ブラシ」「クリーム入れ」などが該当します。化粧に使うもののうち、薬品的なものではなく、「道具」的なものですね。
化粧品を扱う場合には、このような化粧用具も扱うことがあるかと思いますので、21類も登録の必要性がないか検討すべきことになります。
- 44類
- 美容
- 美容情報の提供
44類に属する「美容」というサービス(役務)は、ヘアサロンやネイルサロン、エステサロンのようなサービスを意味します。
また「美容情報の提供」は、たとえばオンラインで美容に役立つ情報を発信するようなサービスが該当する可能性があります。
商品としての化粧品を取り扱う場合、そこから派生してこれらのようなサービスへも展開する場合があり得ます。そのため、44類も登録を検討すべき区分と言えるでしょう。
3. 商標の化粧品の注意点
「化粧品」は、数ある商標登録の中でもよく出願されるジャンルです。
そのため商標登録上の競合が多くなりがちです。そこで、「化粧品」のジャンルにおける商標の注意点をいくつかご紹介します。
- 商標に特徴(識別力)がないと判断されやすい
- パッケージの表現によっては商標権侵害になることも
- 「ブランド名 + 特徴がない言葉」の出願で確実に権利侵害を防ごう
①商標に特徴(識別力)がないと判断されやすい
化粧品業界は、商品の効能の優位性や特徴を直感的に消費者に伝えることが重要なため、他の分野よりも、商品名やキャッチコピーなどにおいて、効能を説明するような意味合いの表現が多く見られます。
そのため、多少の工夫の見られるネーミングやコピーであっても、「よくある表現」と評価されやすく、商標登録の審査においても「商標に特徴(識別力)がないから登録は認められない」と判断されやすくなります。
特に、出願された商標の表現と似たような第三者による使用例がインターネット検索で見つかるような状況だと、特許庁の審査で「特徴がないからNG」と判断されるリスクが高まります。
化粧品分野で商標登録をするときには、その商標に十分な独自性があるか、特に気にするようにしましょう。
たとえば以下は、実際に「特徴がないからNG」と特許庁に判断された例です。
特徴がないと判断された例
- モイストアップブースターローション(不服2020-10892)
- パーフェクト泡洗顔(不服2019-9167)
審判までいくと特徴があると覆ることもある
特許庁で行われる商標登録の審査には大きく2段階あります。もし1段階目の「審査」と呼ばれるフェーズでは登録NGとなっても、それを不服として上訴(正確には「審判請求」といいます)することで、2段階目の「審判」と呼ばれるフェーズで登録OKとなることもあります。
以下は、審査ではダメだったものの、審判で登録OKと判断が覆った事例です。
- しっとり美容シート(不服2020-3554)
- しっとり美肌(不服2020-3553)
- AMINOBOOSTER(不服2021-184)
- はだごこち(不服2019-12424)
OKとNGのボーダーラインは、はっきりと決まったものはありません。単純に商標名だけで決まるものではなく、権利を取ろうとしている商品・サービス内容との関係や、似たような表現を他の人がどのくらい使っているか(どのくらいありふれた表現かどうか)などの事情を総合的に考慮して、ケースバイケースで判断されます。
②パッケージの表現によっては商標権侵害になることも
先にも書いたように、化粧品業界は、商品の効能の優位性や特徴を直感的に消費者に伝えるようなキャッチコピーなどを使うことが比較的多いです。そして、そのようなコピーについて商標登録を試みることも多く行われています。
商品の効能などを直接的に理解させるようなコピーは商標登録が認められにくくはありますが、それでも少しでも独創性があるものについては、ギリギリ登録になる例も少なくありません。
そのため、商品名・ブランド名だけでなく、そのほかパッケージ中で使われている文言の表現によっては、知らないうちに他社の登録商標を使ってしまうこともあります。
たとえば、下記のような表現が商標登録されています。
- 「キンキンヒエヒエ」商標登録第5304857号
- 「うるおいピュア」商標登録第5089949号
- 「サラサラフィット」商標登録第3275166号
このような文言は、うっかり知らずにパッケージなどで使ってしまいそうですよね。
化粧品分野はこのような商標登録が多くあるため、商品名やブランド名以外の文言であっても、必ず商標調査をして問題がないことを確認してから使うようにしましょう。
③「ブランド名 + 特徴がない言葉」の出願で確実に権利侵害を防ごう
②のようなことを考えると、「特徴(識別力)がない言葉」であってもパッケージなどで使用するのが心配になってしまいますよね。
一つの対策として、「ブランド名+特徴がない言葉」で出願し商標登録をしておく、というやり方があります。
たとえば、以下のような商標登録のやり方です。
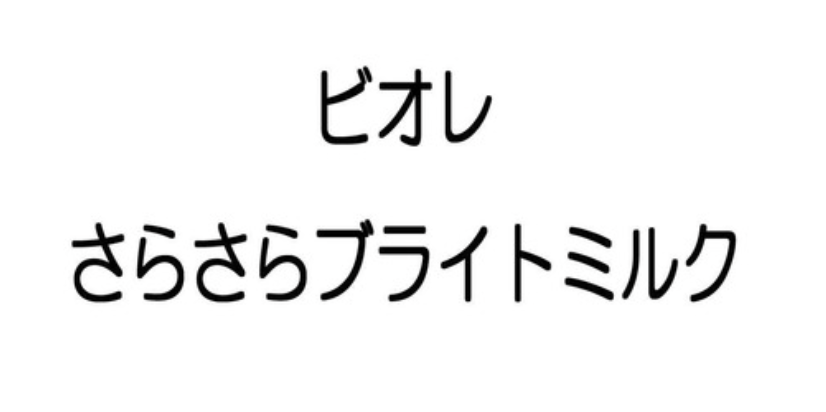
商標登録第5889193号
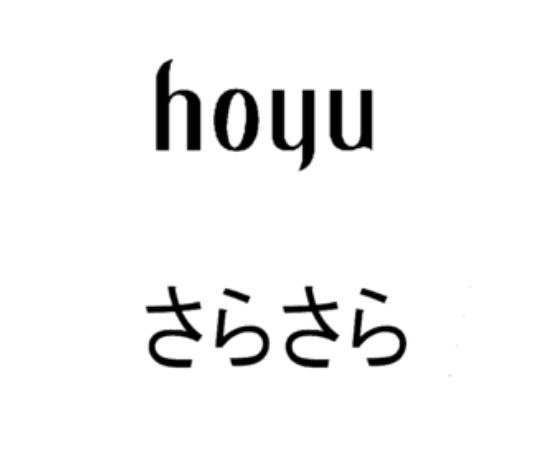
商標登録第5677514号
このように、「特徴のあるブランド名」(上の例では「ビオレ」や「hoyu」)を商標の構成中に含めて出願すると、次のような効果が期待できます。
- 商標登録できる可能性が高くなる
- 「特徴がない言葉」の部分だけを他人が商標登録しようとしたときに、それをブロックできる可能性が高くなる
まず1については、「特徴がない言葉」だけだと商標登録はなかなか特許庁に認めてもらえません。でも、商標登録の可否はあくまでも「商標全体」で判断されるため、商標中に「特徴のあるブランド名」が含まれていれば、「(特徴のある)ブランド名+特徴がない言葉」全体としては商標登録を認めてもらえるのです。
「特徴がない言葉」だけで出願して審査に通過できなかった場合には何も権利が持てませんが、「ブランド名+特徴がない言葉」で登録できれば、ひとまずその「特徴がない言葉」に関して何らかの権利を持つことができます。
では、この「ブランド名+特徴がない言葉」の形で商標登録して意味があるのか?という点が気になるかと思います。これが上記の②になります。
厳密にはケースバイケースの判断にはなるのですが、上記の登録例のように「ブランド名」と「特徴がない言葉」を分離したレイアウトで登録した場合には、後からこの「特徴がない言葉」だけを誰かが出願したときに、特許庁の審査でこれをブロックしてくれる可能性がそれなりに見込めます。
なぜなら、「A+B」という構成の商標があったときに、この商標を「A」と類似、あるいは「B」と類似、というように判断してもよい、という判断手法が商標実務上あるためです。
具体例でいうと、たとえば上記の登録例の「hoyu/さらさら」が先に登録されている場合、他の人が後から「さらさら」の文字を商標登録出願するとどうなるでしょうか?
この場合、「さらさら」の商標登録の審査において、
- 「さらさら」は商標登録を認められるだけの特徴がない
- 仮に特徴があったとしても、「hoyu/さらさら」と類似するから商標登録は認められない
という審査判断がされる可能性が高くなります。このように、いわば「2段構え」の理由で商標登録がブロックされるのです。他の人が「さらさら」を商標登録してしまうことをブロックできれば、自分が「さらさら」を使う安全性は確保できます。
もし「hoyu/さらさら」を商標登録していなかったとしたら、他の人が「さらさら」を出願したときに①しか問題にならないため、反論などで①をクリアされてしまったときに「さらさら」の権利が他人に取られてしまいます。
このような意味で、自分がパッケージなどに使おうとしている「特徴がない(かもしれない)言葉」について、「ブランド名+特徴がない言葉」の形で商標登録することにも意味があるのです。
4. 化粧品を商標登録するときの費用
化粧品分野で商標登録するときの費用は、以下のとおりです。
他の分野での商標登録と変わらず、指定する「区分」の数によって費用が変動します。
- 1区分
- 特許庁に支払う印紙代
- 出願時:12,000円
- 登録時(5年):17,200円
- 専門家の手数料(弁理士などに依頼する場合のみ)
- 10,000~100,000円程度
- 特許庁に支払う印紙代
- 2区分
- 特許庁に支払う印紙代
- 出願時:20,600円
- 登録時(5年):34,400円
- 専門家の手数料(弁理士などに依頼する場合のみ)
- 20,000~150,000円程度
- 特許庁に支払う印紙代
- 3区分
- 特許庁に支払う印紙代
- 出願時:29,200円
- 登録時(5年):51,600円
- 専門家の手数料(弁理士などに依頼する場合のみ)
- 30,000~200,000円程度
- 特許庁に支払う印紙代
商標登録についてより詳しくは、こちらの記事もご覧ください。
まとめ
最後にまとめです。
- 商標登録をするときの化粧品の区分は「3類」。この区分が最も重要
- メインとなる「3類」のほかにも、たとえば以下のような区分でも登録を検討するとよい
- 35類
- 5類
- 21類
- 44類
- 「化粧品」は、商標登録上の競合が多くなりがち。そのため以下のような点に注意しよう
- 商標に特徴(識別力)がないと判断されやすい
- パッケージの表現によっては商標権侵害になることも
- 「ブランド名 + 特徴がない言葉」の出願で確実に権利侵害を防ごう
- 化粧品分野で商標登録するときも、費用は通常と同じ
化粧品の商標登録には、この分野特有のポイントがいくつもありましたね。
商標登録したい人が多いだけに、商標登録への対処に失敗するとトラブルになるリスクも高い分野ですので、あらかじめポイントを押さえて、スマートに商標登録をしていきましょう。
